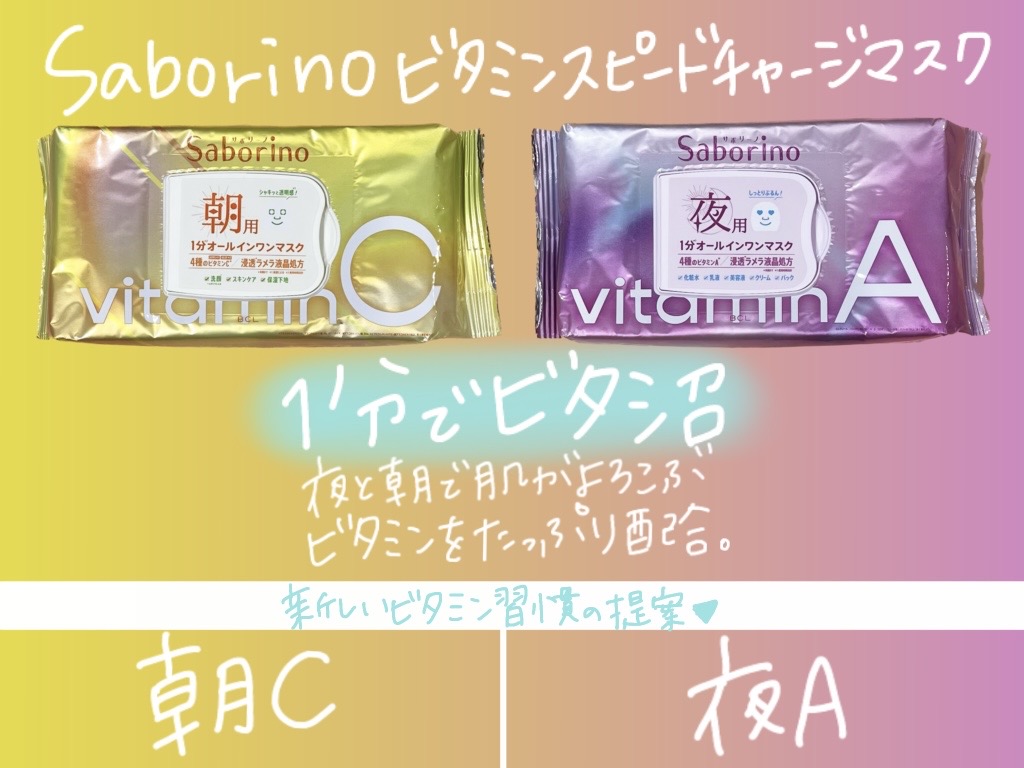お出かけを楽しみたいのに「乗り物酔い」が不安という方も多いのではないでしょうか。
乗り物酔いは脳の混乱が主な原因です。しかし、ほかにもさまざまな原因があり、対策することで症状が緩和できる可能性があります。
今回は、乗り物酔いの原因と自分でできる対策方法をご紹介します。
乗り物酔いは脳の混乱が主な原因です。しかし、ほかにもさまざまな原因があり、対策することで症状が緩和できる可能性があります。
今回は、乗り物酔いの原因と自分でできる対策方法をご紹介します。
乗り物酔いは「脳の混乱」

乗り物酔いとは、車や電車、飛行機などの乗り物に乗っているときに、吐き気や頭痛、めまいなどの症状が出ることです。
乗り物酔いは、内耳の平衡感覚器官と視覚情報の不一致により、脳が混乱することで引き起こされます。
この脳の混乱は、内耳はからだの揺れ動きを感じているのに、目で見ている景色は静止しているため、情報が合わないのが原因です。
乗り物酔いは、内耳の平衡感覚器官と視覚情報の不一致により、脳が混乱することで引き起こされます。
この脳の混乱は、内耳はからだの揺れ動きを感じているのに、目で見ている景色は静止しているため、情報が合わないのが原因です。
乗り物酔いの原因は「揺れ」だけじゃない

乗り物酔いの原因は、前述した揺れと視覚による脳の混乱だけではありません。
下記のような外的・内的要因も乗り物酔いに関係しています。
下記のような外的・内的要因も乗り物酔いに関係しています。
- においや温度といった乗り物内の環境
- 疲労
- ストレス
- 睡眠不足
- 空腹・満腹状態
- 乗り物酔いに対する不安感
乗り物酔いすることが多い方は「また酔ったらどうしよう」「乗り物の中で吐きたくない」などの不安感から、症状がひどくなってしまう場合があります。
また、普段は症状が出ない方でも、疲労・ストレスの蓄積や乗り物内の環境によって、乗り物酔いする可能性が高くなるので注意しましょう。
また、普段は症状が出ない方でも、疲労・ストレスの蓄積や乗り物内の環境によって、乗り物酔いする可能性が高くなるので注意しましょう。
お出かけの不安が減る! 乗り物酔い克服方法

乗り物酔いを克服・予防する方法を3つご紹介します。
からだの調子を整えておく
体調不良や疲労、ストレスは乗り物酔いを引き起こす可能性があります。
お出かけ前の数日間は睡眠や休息を十分にとり、体力・気力を回復させておきましょう。
また、空腹や過度な満腹状態も乗り物酔いの原因となります。
乗り物酔いが心配なときは、腹7〜8分目ほどの量の食事を摂っておくことを心がけましょう。
お出かけ前の数日間は睡眠や休息を十分にとり、体力・気力を回復させておきましょう。
また、空腹や過度な満腹状態も乗り物酔いの原因となります。
乗り物酔いが心配なときは、腹7〜8分目ほどの量の食事を摂っておくことを心がけましょう。
楽な服装で出かける
からだを締め付ける服や車内の温度に合わない厚着・薄着は、乗り物酔いの原因になることがあります。
とくに腹部の締め付けは、吐き気や気持ち悪さにつながりやすくなります。
乗り物酔いを防ぐには、ハイウエストのスキニージーンズやタイトスカートなどは避けて、なるべくからだを締め付けない服を選びましょう。
また、着脱しやすいパーカーやカーディガンなどの上着を1枚持っておくと、乗り物内の温度に合わせて調節しやすいので安心です。
とくに腹部の締め付けは、吐き気や気持ち悪さにつながりやすくなります。
乗り物酔いを防ぐには、ハイウエストのスキニージーンズやタイトスカートなどは避けて、なるべくからだを締め付けない服を選びましょう。
また、着脱しやすいパーカーやカーディガンなどの上着を1枚持っておくと、乗り物内の温度に合わせて調節しやすいので安心です。
気分を紛らわせる
乗り物内の音やにおいなどの、環境によって酔いやすい方は、気分を紛らわせる方法がおすすめです。
音楽を聴いたり、すっきりするアロマをかいだり、自分の世界に没頭してみましょう。
同行者がいるときは、会話を楽しむのも有効です。
話が弾んで、乗り物酔いせずにいつのまにか目的地についているかもしれません。
音楽を聴いたり、すっきりするアロマをかいだり、自分の世界に没頭してみましょう。
同行者がいるときは、会話を楽しむのも有効です。
話が弾んで、乗り物酔いせずにいつのまにか目的地についているかもしれません。
乗り物酔い対策には漢方もおすすめ

乗り物酔い対策には、漢方薬もおすすめです。
乗り物酔いの原因は、耳の三半規管が刺激を受けることによる自律神経の乱れ、水分代謝のアンバランス、疲労・ストレスの蓄積、乗り物酔いに対する不安感、睡眠不足などが挙げられます。
乗り物酔い対策には、
乗り物酔いの原因は、耳の三半規管が刺激を受けることによる自律神経の乱れ、水分代謝のアンバランス、疲労・ストレスの蓄積、乗り物酔いに対する不安感、睡眠不足などが挙げられます。
乗り物酔い対策には、
- 体内の水分バランスを整えて、めまいや吐き気を抑える
- 自律神経の乱れを整えて、睡眠の質を高めたり、ストレスによる車酔いを改善したりする
- 消化・吸収機能を改善して心とからだを元気にする
などの作用をもつ漢方薬を選びましょう。
漢方薬は、心とからだのバランスを整えて根本的な体質改善を目指すので、乗り物酔いが心配な方にとくにおすすめです。
<乗り物酔い対策におすすめの漢方薬>
五苓散(ごれいさん)
水分代謝を促し、全身の水分バランスを整えます。
むくみや吐き気、めまいや頭痛、二日酔いなどに幅広く用いられます。
むくみや吐き気、めまいや頭痛、二日酔いなどに幅広く用いられます。
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
「気(エネルギー)」の停滞を取り除き、精神の緊張を和らげます。
精神不安やイライラ、不眠に用いられることが多いです。
精神不安やイライラ、不眠に用いられることが多いです。
<漢方薬を選ぶ際の重要なポイント>
漢方薬の効果を最大限に高めるには、自分の体質や症状に合ったものを選ぶことが大切です。
合っていなければ、効果を感じられないだけでなく、場合によっては副作用が生じることもあります。
どの漢方薬が自分に合っているのかを見極めるためには、漢方専門の薬剤師の力を借りましょう。
最近では、漢方に詳しい薬剤師がAIを活用して、個人に効く漢方薬を見極めてくれ、お手頃価格で自宅まで郵送してくれる「あんしん漢方」などのオンライン漢方相談も登場しています。
自分に合う漢方薬を気軽に試せる便利なサービスなので、漢方が初めての方にもおすすめです。
体質診断から漢方薬の購入までスマホ1台ですべて完結でき、家にいながら専門的なサービスを受けられます。
漢方医師による定期的な経過観察もあるので、効き目を見ながら処方薬の変更も行えます。
●あんしん漢方:https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=21243ze0kire0061
合っていなければ、効果を感じられないだけでなく、場合によっては副作用が生じることもあります。
どの漢方薬が自分に合っているのかを見極めるためには、漢方専門の薬剤師の力を借りましょう。
最近では、漢方に詳しい薬剤師がAIを活用して、個人に効く漢方薬を見極めてくれ、お手頃価格で自宅まで郵送してくれる「あんしん漢方」などのオンライン漢方相談も登場しています。
自分に合う漢方薬を気軽に試せる便利なサービスなので、漢方が初めての方にもおすすめです。
体質診断から漢方薬の購入までスマホ1台ですべて完結でき、家にいながら専門的なサービスを受けられます。
漢方医師による定期的な経過観察もあるので、効き目を見ながら処方薬の変更も行えます。
●あんしん漢方:https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=21243ze0kire0061
乗り物酔いを克服しよう
乗り物酔いは、脳の混乱以外にも、乗り物内の環境や自分の体調など、さまざまな要因が重なることで起こりやすくなります。
予防するには、からだの負担を減らしたり、気を紛らわせたりしましょう。
また、専門家に相談して漢方薬で酔いにくい体質を目指すのもおすすめです。
乗り物酔いを克服して、不安のないお出かけを楽しみましょう!
予防するには、からだの負担を減らしたり、気を紛らわせたりしましょう。
また、専門家に相談して漢方薬で酔いにくい体質を目指すのもおすすめです。
乗り物酔いを克服して、不安のないお出かけを楽しみましょう!
<この記事を書いた人>
あんしん漢方 ライター
円山 真由佳(えんやま まゆか)
医薬品登録販売者。ドラッグストアでの医薬品・化粧品販売を経て、市販薬の使い分け方を広めるべく執筆・情報発信を行う。美容薬学・アロマテラピーの資格を保持し、インナーケアや女性の不調ケアにも精通している。
表面的な悩みの奥にある潜在的な悩みをくみとり、対症療法ではなく根本改善を目的としたアドバイスを得意とする。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホ一つで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でもサポートを行っている。
円山 真由佳(えんやま まゆか)
医薬品登録販売者。ドラッグストアでの医薬品・化粧品販売を経て、市販薬の使い分け方を広めるべく執筆・情報発信を行う。美容薬学・アロマテラピーの資格を保持し、インナーケアや女性の不調ケアにも精通している。
表面的な悩みの奥にある潜在的な悩みをくみとり、対症療法ではなく根本改善を目的としたアドバイスを得意とする。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホ一つで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でもサポートを行っている。