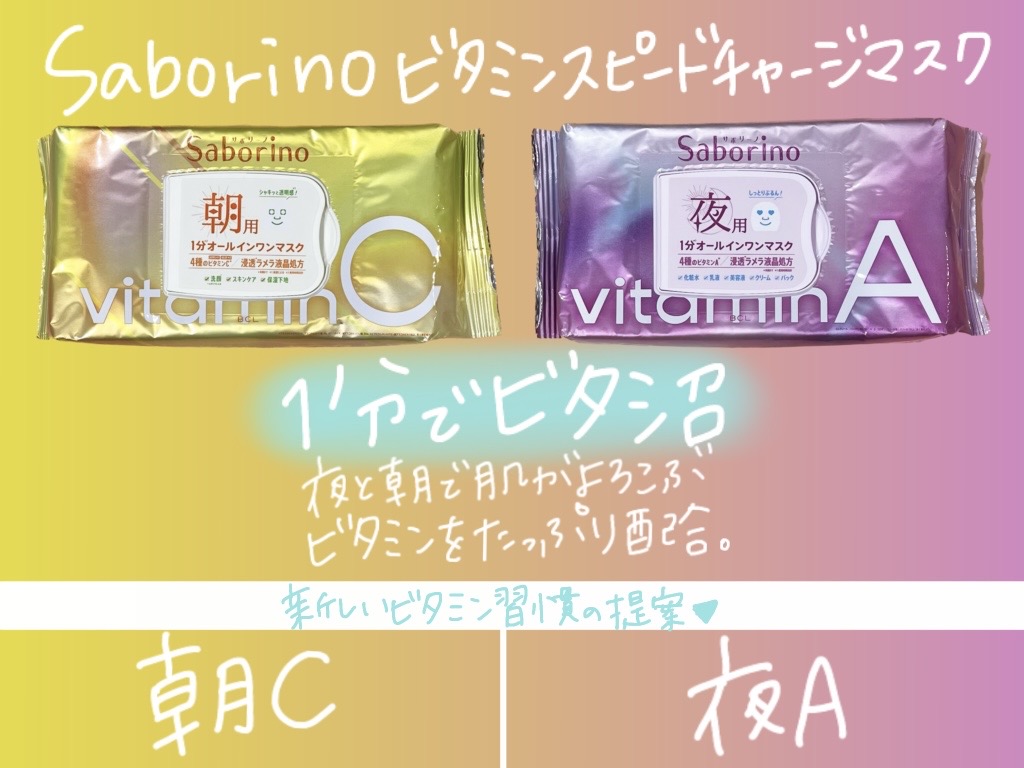気をつけてもなかなか治らない「猫背」にお悩みの方は多いのではないでしょうか?
猫背はスタイルが悪く見えるだけでなく、放置すると肩こりや腰痛、冷えなど、さまざまな不調につながります。
そこで今回は、猫背になる原因と正しい姿勢をつくるコツ、猫背の改善におすすめのストレッチをご紹介します。
猫背はスタイルが悪く見えるだけでなく、放置すると肩こりや腰痛、冷えなど、さまざまな不調につながります。
そこで今回は、猫背になる原因と正しい姿勢をつくるコツ、猫背の改善におすすめのストレッチをご紹介します。
猫背の原因とは?

健康や美容においてさまざまなデメリットをもたらす「猫背」。
改善するには原因を知り、正しい対処法を取り入れることが大事です。
猫背になる原因を3つご説明します。
改善するには原因を知り、正しい対処法を取り入れることが大事です。
猫背になる原因を3つご説明します。
長時間のデスクワークやスマホ操作

デスクワークやスマホ操作などで長時間同じ姿勢をとっていると、猫背になりやすいです。
これらの姿勢は画面に目線を合わせるため、首が前に出て肩が内側に入りやすくなります。
そのため、胸が縮こまって背骨が丸まり、前かがみの姿勢になりがちです。
このような姿勢が長時間続くとからだに歪みが生じ、猫背の姿勢が定着する原因になるのです。
これらの姿勢は画面に目線を合わせるため、首が前に出て肩が内側に入りやすくなります。
そのため、胸が縮こまって背骨が丸まり、前かがみの姿勢になりがちです。
このような姿勢が長時間続くとからだに歪みが生じ、猫背の姿勢が定着する原因になるのです。
筋力の衰え

加齢や運動不足で筋力が衰えることも猫背の原因のひとつです。
正しい姿勢を保持するためには、筋力が必要です。
腹筋や背筋などの胴体を支える筋肉群のほか、背骨や骨盤の動きに関係する体幹部のインナーマッスルが衰えると、上半身を支えきれなくなり、猫背につながります。
たとえば、股関節をまたぐインナーマッスルである腸腰筋が衰えると、骨盤が後傾して背骨が丸まりやすくなるのです。
正しい姿勢を保持するためには、筋力が必要です。
腹筋や背筋などの胴体を支える筋肉群のほか、背骨や骨盤の動きに関係する体幹部のインナーマッスルが衰えると、上半身を支えきれなくなり、猫背につながります。
たとえば、股関節をまたぐインナーマッスルである腸腰筋が衰えると、骨盤が後傾して背骨が丸まりやすくなるのです。
筋肉の柔軟性低下

筋肉の硬さも猫背の原因になります。
仕事や家事など、日常動作の多くはからだの前側で行われます。
そのため、前かがみの姿勢が習慣になると、肩や肩甲骨周辺の筋肉に過剰な負担がかかり、凝り固まって関節の可動域も狭くなり、猫背の姿勢につながるのです。
また、上半身だけでなく、股関節や太ももの筋肉が硬いと筋肉が引っ張られて骨盤が後傾しやすくなるため、猫背の原因になります。
仕事や家事など、日常動作の多くはからだの前側で行われます。
そのため、前かがみの姿勢が習慣になると、肩や肩甲骨周辺の筋肉に過剰な負担がかかり、凝り固まって関節の可動域も狭くなり、猫背の姿勢につながるのです。
また、上半身だけでなく、股関節や太ももの筋肉が硬いと筋肉が引っ張られて骨盤が後傾しやすくなるため、猫背の原因になります。
猫背を改善! 正しい姿勢の作り方
猫背の改善には、原因となる日常の習慣を見直し、正しい姿勢に整えることが大事です。
以下では、猫背を改善するために日常で意識したいコツを3つご紹介します。
以下では、猫背を改善するために日常で意識したいコツを3つご紹介します。
パソコンやスマホ使用時の姿勢を見直す

パソコンやスマホを使用するときの姿勢を見直し、正しい姿勢を意識することで猫背の改善が目指せます。
腹筋を使わず背もたれやソファなどに寄りかかった座り方は、骨盤の歪みを招き、猫背につながります。
座るときは左右のおしりの骨を座面に対して垂直に立て、骨盤を起こして背骨を天井方向へまっすぐ伸ばす意識を持ちましょう。
また、パソコンスタンドなどを利用して画面の高さを目の高さに合わせる、1時間に1回は立ち上がって長時間同じ姿勢にならないようにするなどの工夫も、猫背の予防に役立ちます。
腹筋を使わず背もたれやソファなどに寄りかかった座り方は、骨盤の歪みを招き、猫背につながります。
座るときは左右のおしりの骨を座面に対して垂直に立て、骨盤を起こして背骨を天井方向へまっすぐ伸ばす意識を持ちましょう。
また、パソコンスタンドなどを利用して画面の高さを目の高さに合わせる、1時間に1回は立ち上がって長時間同じ姿勢にならないようにするなどの工夫も、猫背の予防に役立ちます。
姿勢の保持に必要な筋肉を鍛える

猫背の改善には、正しい姿勢を保持するための筋力が必要です。
腹筋や背筋などの体幹部や、骨盤や股関節の動きに関与するお尻や太ももの筋肉、インナーマッスルの腸腰筋などを鍛えましょう。
これらは激しい筋トレをしなくても、軽い運動や日常の動作で鍛えられます。
普段からおなかを引き締めて胸を開き、背筋を伸ばす意識を持つと、上半身を支える筋肉が正しく働きます。
また、定期的な運動習慣を持つようにするほか、歩行や階段の上り下りなどでこまめにからだを動かすことも筋力アップにつながります。
腹筋や背筋などの体幹部や、骨盤や股関節の動きに関与するお尻や太ももの筋肉、インナーマッスルの腸腰筋などを鍛えましょう。
これらは激しい筋トレをしなくても、軽い運動や日常の動作で鍛えられます。
普段からおなかを引き締めて胸を開き、背筋を伸ばす意識を持つと、上半身を支える筋肉が正しく働きます。
また、定期的な運動習慣を持つようにするほか、歩行や階段の上り下りなどでこまめにからだを動かすことも筋力アップにつながります。
筋肉の柔軟性を高める

筋肉は鍛えるだけでなく、ほぐして柔軟性を高めることも大事です。
猫背の姿勢では、からだの前側の胸や股関節の前側、前ももは縮こまって硬くなりがちです。
また、首や肩、肩甲骨周辺の筋肉は、重たい頭や両腕を支えるために引っ張られて緊張することで硬くなります。
これらの筋肉の柔軟性を高めて、全体の筋肉バランスを整えることが姿勢の改善につながります。
筋肉を柔軟にするには、ヨガやストレッチがおすすめです。
猫背の姿勢では、からだの前側の胸や股関節の前側、前ももは縮こまって硬くなりがちです。
また、首や肩、肩甲骨周辺の筋肉は、重たい頭や両腕を支えるために引っ張られて緊張することで硬くなります。
これらの筋肉の柔軟性を高めて、全体の筋肉バランスを整えることが姿勢の改善につながります。
筋肉を柔軟にするには、ヨガやストレッチがおすすめです。
猫背の改善におすすめのストレッチ
猫背の改善には、硬くなった筋肉をゆるめてほぐしながら、必要な筋力を高めるストレッチが効果的です。
以下では、猫背の改善におすすめの簡単ストレッチを2つご紹介します。
以下では、猫背の改善におすすめの簡単ストレッチを2つご紹介します。
コブラストレッチ

おなかをしっかり引き締めながら腰周りの筋肉を強化することで、姿勢の改善が目指せます。
おなかの筋肉を伸ばして胸を開くことで、普段縮みがちなからだの前側の筋肉にアプローチして猫背を改善します。
おなかの筋肉を伸ばして胸を開くことで、普段縮みがちなからだの前側の筋肉にアプローチして猫背を改善します。
- (1) うつ伏せになります。脚は腰幅に開いてまっすぐに伸ばし、おでこを床につけて首の後ろを伸ばします。
- (2) わきを締めた状態でひじを直角に曲げ、手のひらを胸の横につきます。
- (3) 息を吸いながら、手のひらで床を押して顔と上半身を持ち上げ、胸を天井方向へ引き上げます。
このとき、腰を反り過ぎないように、おなかにしっかり力を入れておきましょう。 - (4) さらに手のひらで床を押してひじを伸ばし、おなかも床から浮かせます。
この姿勢のまま30秒キープしましょう。
テーブルトップストレッチ

手足で力強く床を押してからだを持ち上げ、テーブルの形をつくるストレッチです。
お尻が下がらないように、背中全体の筋肉を使って引き上げることで、肩甲骨周辺の筋肉を刺激して背筋を強化し、猫背を改善します。
お尻が下がらないように、背中全体の筋肉を使って引き上げることで、肩甲骨周辺の筋肉を刺激して背筋を強化し、猫背を改善します。
- (1) 両ひざを曲げて座ります。
ひざは90度くらいの角度に曲げ、足は腰幅ほどに開いて安定させます。 - (2) 両手のひらをお尻のやや後ろにつきます。
手は肩幅ほどに開き、手の指先を斜め外側に向けます。 - (3) 背筋を伸ばして肩甲骨を引き寄せながら、両手のひらで床を押してお尻を持ち上げます。
足裏は床を強く押して、テーブルのように胴体からひざまでを、まっすぐに保ちましょう。 - (4) この姿勢のまま30秒キープします。
首がすくまないように、肩を床の方向に下げて胸を開く意識を持ってください。
首を傷めないようにあごを引いておきましょう。
猫背による血行不良には漢方もおすすめ

猫背になるとからだに歪みが生じやすくなり、肩こりや腰痛につながるほか、胸が縮こまって呼吸が浅くなります。
そのため、血行不良を招き、冷えや肩こりなどの不調の原因にもなります。
猫背によるこれらの不調には、漢方薬を活用したからだの内側からのアプローチもおすすめです。
猫背による冷えや肩こりの改善には、「血流をよくして熱を巡らせ、肩の筋肉をゆるめる」「水分の循環をよくして冷えを改善し、老廃物や疲労物質を排出する」「胃腸の働きをよくして熱をつくりだす」などの生薬を含む漢方薬を選びます。
漢方薬には、からだのバランスを整えて代謝や血流を活性化し、人が本来持っている機能性を高めることで、心とからだをより健康な状態に向かわせるという特徴があります。
そのため、不調を根本から改善し、不調の起こりにくい体質を目指せるのです。
しかも、自然の生薬でできた漢方薬なら、一般的に副作用が少ないとされているので安心です。
自分に合ったものを毎日飲むだけなので、手軽なヘルスケアとして、ストレッチとあわせて取り入れてみてはいかがでしょうか。
そのため、血行不良を招き、冷えや肩こりなどの不調の原因にもなります。
猫背によるこれらの不調には、漢方薬を活用したからだの内側からのアプローチもおすすめです。
猫背による冷えや肩こりの改善には、「血流をよくして熱を巡らせ、肩の筋肉をゆるめる」「水分の循環をよくして冷えを改善し、老廃物や疲労物質を排出する」「胃腸の働きをよくして熱をつくりだす」などの生薬を含む漢方薬を選びます。
漢方薬には、からだのバランスを整えて代謝や血流を活性化し、人が本来持っている機能性を高めることで、心とからだをより健康な状態に向かわせるという特徴があります。
そのため、不調を根本から改善し、不調の起こりにくい体質を目指せるのです。
しかも、自然の生薬でできた漢方薬なら、一般的に副作用が少ないとされているので安心です。
自分に合ったものを毎日飲むだけなので、手軽なヘルスケアとして、ストレッチとあわせて取り入れてみてはいかがでしょうか。
<血行不良や肩こりにおすすめの漢方薬>
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
冷え症で、体力がなく、貧血のある方。
血(けつ)を補い、血の巡りをよくすることで、筋肉に栄養を与えて肩こりに働きかけます。
血(けつ)を補い、血の巡りをよくすることで、筋肉に栄養を与えて肩こりに働きかけます。
大柴胡湯(だいさいことう)
体力があり、筋肉質で、肩こりがある方。
気の流れをよくして、筋肉の緊張をほぐすことで肩こりに働きかけます。
ストレスや高血圧による肥満や肩こり、頭痛、便秘などの諸症状に用いられています。
気の流れをよくして、筋肉の緊張をほぐすことで肩こりに働きかけます。
ストレスや高血圧による肥満や肩こり、頭痛、便秘などの諸症状に用いられています。
<漢方薬を選ぶ際の重要なポイント>
漢方薬を選ぶ際は、自分に合ったものを選ぶことが重要です。
自分の状態や体質に合っていないと、効果を感じられないだけでなく、場合によっては副作用が生じる場合もあります。
どの漢方薬が自分に合っているのかを見極めるためには、漢方に精通した薬剤師の力を借りるのがおすすめです。
最近では、オンライン上で漢方の相談ができるサービスも出てきています。
漢方に詳しい薬剤師がAIを活用して個人に効く漢方薬を見極め、お手頃価格で自宅まで郵送してくれる「あんしん漢方」などのオンライン漢方サービスに、一度相談してみるのもいいでしょう。
体質診断から漢方薬の購入までスマホ1台ですべて完結でき、家にいながら専門的なサービスを受けられます。
漢方医師による定期的な経過観察もあるので、効き目を見ながら処方薬の変更も行えます。
●あんしん漢方:https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=21243ze0kire0061
自分の状態や体質に合っていないと、効果を感じられないだけでなく、場合によっては副作用が生じる場合もあります。
どの漢方薬が自分に合っているのかを見極めるためには、漢方に精通した薬剤師の力を借りるのがおすすめです。
最近では、オンライン上で漢方の相談ができるサービスも出てきています。
漢方に詳しい薬剤師がAIを活用して個人に効く漢方薬を見極め、お手頃価格で自宅まで郵送してくれる「あんしん漢方」などのオンライン漢方サービスに、一度相談してみるのもいいでしょう。
体質診断から漢方薬の購入までスマホ1台ですべて完結でき、家にいながら専門的なサービスを受けられます。
漢方医師による定期的な経過観察もあるので、効き目を見ながら処方薬の変更も行えます。
●あんしん漢方:https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=21243ze0kire0061
猫背を改善してスタイルも気分もアップ!
見た目にも健康面にも多くのデメリットをもたらす、「猫背」の改善におすすめのストレッチを2つご紹介しました。
猫背は、スマホ世代の現代人に多い悩みのひとつといえます。
改善には、原因となる姿勢を正すほか、姿勢の保持に必要な筋肉を育むことと、筋肉をほぐして柔軟にすることの両方が大事です。
ご紹介したストレッチで猫背の原因となる筋肉にアプローチし、正しい姿勢に整えて猫背を改善しましょう。
猫背は、スマホ世代の現代人に多い悩みのひとつといえます。
改善には、原因となる姿勢を正すほか、姿勢の保持に必要な筋肉を育むことと、筋肉をほぐして柔軟にすることの両方が大事です。
ご紹介したストレッチで猫背の原因となる筋肉にアプローチし、正しい姿勢に整えて猫背を改善しましょう。
<この記事を書いた人>
ヨガインストラクター・ライター 古城美季(こじょうみき)
2015年にRYT200(全米ヨガアライアンス認定)を修了し、3000時間以上の指導歴と、インストラクターのトレーナーとしての経験を持つ。ひとりひとりの心と身体に合わせたパーソナルなレッスンが得意。現在は、自分に適した漢方薬を、お手頃価格で自宅に郵送してくれる「あんしん漢方」などで兼業ライターとしても活躍。ヨガと言葉を通して「心身の健康」や「心豊かな暮らし」のサポートができるよう心掛けている。
2015年にRYT200(全米ヨガアライアンス認定)を修了し、3000時間以上の指導歴と、インストラクターのトレーナーとしての経験を持つ。ひとりひとりの心と身体に合わせたパーソナルなレッスンが得意。現在は、自分に適した漢方薬を、お手頃価格で自宅に郵送してくれる「あんしん漢方」などで兼業ライターとしても活躍。ヨガと言葉を通して「心身の健康」や「心豊かな暮らし」のサポートができるよう心掛けている。